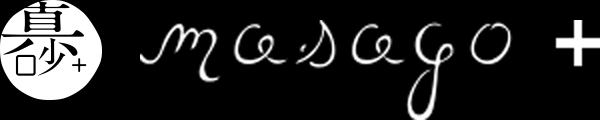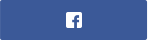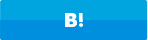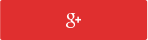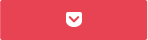今春、有限会社 真砂は17年目の春を迎えることになる。
「真砂のとうふ」は益田市内では広く知られるところとなり、学校や公民館と連携した地域商社としての取り組みは、過疎地域の事例として大臣表彰を受けるまでになった。
しかし、本当にこれでよかったのだろうか?
真砂地区の人口は昨年とうとう400名を割ったものの、地域自治組織が設立されるなど、課題を克服し、持続可能な場所であり続けるための取り組みが住民の間ですすめられている。
本当の正念場はこれからだ。
(有)真砂が生まれた当時は、むらおこし的なイベントを盛大に開催し、地域住民が一丸となって真砂を盛り上げた。
その熱はすばらしく高かったが、冷めるのも早かった。
学校・公民館・地域商社の協働による食と農を活かした地域づくりは、その課題を克服するために、小さくても絶え間なく動くエンジンを日々の「なりわい」中にみつけだすことだった。
もっと言ってしまうと、地域運営の戦術変更を行ったのだ。
そして今、また真砂はすでに変わろうとしている。
過疎問題は、かつて過疎地域だけの問題であった。
しかし日本の人口が都市部をのぞくあらゆる地域で減少していくことが歴然となった今、大きな社会問題として認められつつある。
その対処法には様々な処方箋が存在し、突出した成功事例は称賛されている。
どうやら課題は奮闘すれば解決され、事態はv字回復していくという幻想がいまだ残存しているようだ。
未来の山里のすがたは、一日という時間に喩えるなら、もはや日没だ。
真砂地区の日晩山(ひぐらしやま)に関する伝承に以下のような古句がある。
「ひぐらしの山路をくらみ小夜ふけて 木の末ごとに紅葉照らせり」
道真公もしくは和泉式部が旅の途上日暮れて真砂に立ち寄り詠じたというのだ。
この句のように、暮れていく世情にありつつも、闇のモミジが明るいと言い切れる思考がこれからの私たちには求められているように思う。
小さくても美しく、末永く続いていく山里に真砂が成ればと瞳を上に向けて、私は今日も豆腐を造る。